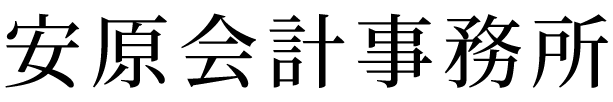中小企業における社員教育といえば、OJT(On the Job Training)が中心という会社が多いのではないでしょうか。先輩社員が新入社員に実務を教えるスタイルは確かに有効ですが、「教えっぱなし」「学びっぱなし」になってしまうと、育成効果は半減してしまいます。
これからの時代は、OJTに頼りきりにせず、意図的な「教育の仕組み」を社内に築くことが重要です。今回は、OJTをベースにしながら、さらに育成効果を高めるための5つの具体策をご紹介します。
目次
- なぜOJTだけでは育たないのか?教育の仕組みの必要性
- OJTで終わらせない教育の仕組み①:育成のゴールを明確にする
- OJTで終わらせない教育の仕組み②:教える側に“指導マニュアル”を渡す
- OJTで終わらせない教育の仕組み③:定期的な振り返り・面談を仕組みにする
- OJTで終わらせない教育の仕組み④:“集合教育”と組み合わせる
1. なぜOJTだけでは育たないのか?教育の仕組みの必要性
OJTは、「実務を通じて学ばせる」という点で非常に実践的な手法です。しかし、OJTだけでは以下のような問題が起こりがちです。
- 教える内容や質が人によってバラバラ
- 教える側の力量に依存してしまう
- 受け身のまま、スキルが定着しない
- 体系的な知識・理論が身につかない
つまり、属人的で場当たり的な教育になりやすいのです。OJTは万能ではありません。むしろ、OJTを効果的に機能させるには、「誰が教えても、誰が受けても、一定以上の成長ができる仕組み」が必要なのです。
この仕組みが整っていれば、教える側の負担も軽減され、育成の再現性も高まります。今後の成長を支えるためにも、組織として教育を“設計”する視点が不可欠です。
2. OJTで終わらせない教育の仕組み①:育成のゴールを明確にする
育成を成功させる第一歩は、「何をもって一人前とするか」を明確に定義することです。ゴールが曖昧なままでは、教える側も教わる側も手探り状態が続き、育成に時間がかかります。
たとえば、営業職であれば、
- 入社6ヶ月以内に月3件以上の新規受注
- 商談同行なしで受注できるレベル
経理職であれば、
- 月次決算を一人で完結できる
- 経費精算業務を独力でミスなく処理できる
といった具合に、「どのレベルに到達すれば一人前か」を具体的に設定しましょう。これを「育成ゴールシート」としてまとめ、教える側・教わる側の双方で共有することが効果的です。ゴールがはっきりすれば、育成スピードも飛躍的に高まります。
3. OJTで終わらせない教育の仕組み②:教える側に“指導マニュアル”を渡す
OJTの成否は、実は「教える側」に大きく左右されます。しかし現場では、教える社員自身が「どう教えればいいか分からない」「自己流でやっている」というケースが珍しくありません。
そこで必要なのが、「指導マニュアル」の整備です。指導マニュアルとは、たとえばこんな内容をまとめたものです。
- 新人が初めに覚えるべき仕事一覧
- 各業務の教え方(手順・ポイント・注意点)
- 教える際の心構え(押し付けず、質問を引き出す など)
これを渡すことで、教える社員は迷わず指導に臨めるようになります。さらに、指導の質も標準化され、誰が教えても一定のレベルを保てるようになります。結果、OJTの属人化を防ぎ、育成の質を高めることができるのです。
4. OJTで終わらせない教育の仕組み③:定期的な振り返り・面談を仕組みにする
OJTを行っていても、フォローアップがなければ、「やったつもり」「教わったつもり」で終わってしまう危険性があります。そこで効果的なのが、定期的な振り返り・面談の仕組みです。
たとえば、
- 1か月ごとにOJT担当者と育成対象者で進捗面談
- 面談では「できるようになったこと」「できなかったこと」「次回までの目標」を整理する
この振り返りを仕組み化することで、OJTの内容が“点”ではなく“線”につながり、成長のスピードが格段に上がります。
さらに、面談を通じて悩みや課題を早期に拾うことができるため、挫折や離職の防止にもつながります。ポイントは、「褒める・認める」フィードバックを必ず入れること。これがモチベーションを維持する鍵になります。
5. OJTで終わらせない教育の仕組み④:“集合教育”と組み合わせる
OJTは現場力を養うには最適ですが、体系的な知識や基礎理論を身につけるにはやや不足しがちです。そこでおすすめなのが、集合教育(座学研修)との組み合わせです。
たとえば、
- 社内で年2回、テーマ別の基礎研修を実施(例:ビジネスマナー、営業スキル、業界知識)
- 社外セミナーやオンライン講座を活用して基礎力を底上げ
集合教育を取り入れることで、社員同士の学びの場が生まれ、横のつながりも強化されます。さらに、座学で得た知識を現場のOJTで実践することで、学びが定着しやすくなります。
「現場」と「理論」をバランスよく組み合わせる。この工夫が、OJTを単なる“経験の場”に終わらせないためのカギになります。
まとめ
OJTは非常に優れた育成手法ですが、それだけに頼っていては組織の成長スピードに限界が訪れます。ゴール設定、指導マニュアル、定期的な面談、そして座学の導入。これらを組み合わせることで、社員一人ひとりが着実に成長し、自律的に動ける組織をつくることができます。
「OJTを超えた教育」を仕組みとして整備し、会社全体の底力を引き上げていきましょう。
次回のテーマは「中小企業のためのキャッシュ管理法」を予定しています。