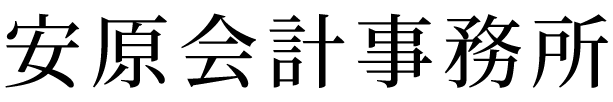経営のかじ取りを担う経営層は、単なる意思決定者にとどまらず、現場の活力を引き出す存在でもあります。ところが、経営層と現場の間に溝がある企業は少なくありません。戦略を立てても現場に響かない、指示が伝わっても動きが鈍い——その原因の一端は、経営層自身の「現場力」の不足にあります。
今回は「現場力を高める経営層の育て方」をテーマに、経営層が現場とつながり、組織を動かすリーダーへと成長するためのポイントを紐解いていきます。

【目次】
- 現場力を高める経営層が必要な理由
- 現場力を高める経営層に求められる視点
- 現場力を高める経営層を育てる仕組み
- 現場力を高める経営層の行動習慣
- 現場力を高める経営層の育成効果の測定
【本文】
1.現場力を高める経営層が必要な理由
経営層の現場力とは、現場の状況を正確に理解し、現場の力を引き出すために自ら動ける力です。現場力のある経営層は、机上の空論にとどまらず、現場のリアルな課題に寄り添いながら意思決定を行います。その結果、現場の納得と共感を得られやすくなり、戦略の実行力が格段に高まります。
一方で、現場と距離のある経営層は、「指示待ち組織」をつくる要因になります。現場の声が反映されない計画は形骸化し、社員の士気も下がっていきます。だからこそ、経営層こそが現場に出て、現実を知り、共に動く姿勢が求められます。
2.現場力を高める経営層に求められる視点
現場力を高めるには、視座・視野・視点の3つの視点が必要です。「視座」は高く、会社全体を見渡す経営的な視点。「視野」は広く、部門横断的な連携を意識したマネジメント視点。そして「視点」は近く、現場の細部に目を配るオペレーション視点です。
経営層がこの3つの視点を使い分けながら意思決定できるようになることで、現場との距離が縮まり、実効性のあるリーダーシップが生まれます。また、現場との「対話の量」が大きなカギになります。観察し、聞き、フィードバックする。こうした地道な姿勢が、現場力向上には欠かせません。
3.現場力を高める経営層を育てる仕組み
属人的に育つのを待つのではなく、育成の仕組みをつくることが重要です。たとえば、定期的に現場に足を運ぶ「経営現場同行制度」や、若手社員との意見交換会などを制度化することで、経営層が現場と接する機会を意図的に設けます。
また、経営会議や戦略立案の際には、現場の情報を一次情報として扱うようにし、経営層自身が現場ヒアリングを行ったうえで意思決定に臨む習慣をつけましょう。育成対象者に対するメンター制度やOJTなども有効です。外部の視点を入れるために、コンサルタントや専門家の支援を受けるのもひとつの方法です。
4.現場力を高める経営層の行動習慣
経営層が現場力を身につけるには、日々の行動習慣の積み重ねが必要です。たとえば、「毎週1部署を訪問して3人の社員と会話する」「週1回は現場日報をすべて読む」「気づいた点を必ずフィードバックする」など、小さくても確実に行える行動目標を設定します。
また、社員の行動と成果をしっかり観察し、経営視点からのフィードバックを惜しまないことも大切です。現場からの信頼は、継続的な関与と対話から生まれます。計画を立て、実行し、振り返り、改善するPDCAサイクルを自ら回す姿勢が、現場力の基盤となるのです。
5.現場力を高める経営層の育成効果の測定
育成の効果を可視化することで、改善点が明確になり、次のアクションにつなげやすくなります。定量的には「現場訪問数」「現場との対話時間」「フィードバックの回数」などを指標化し、定性的には「社員からの信頼度」や「現場での会話の質」などを評価します。
定期的な360度フィードバックや、現場リーダーとの1on1で得られる声をもとに、経営層自身の気づきにつなげていく仕組みも有効です。育成を一過性に終わらせず、継続的に取り組むことで、経営層全体の「現場感度」が磨かれ、組織全体に前向きな変化が起こります。
【まとめ】
現場力のある経営層がいる会社は、組織のエネルギーが強く、変化に柔軟に対応できる土台があります。現場を理解し、現場を動かし、現場と共に進む。その姿勢こそが、経営を動かす力になります。
経営層の育成は、組織の未来への投資です。計画的に、継続的に、そして本気で向き合いましょう。
次回のテーマは「業務の見える化で無駄を削減」を予定しています。